エントリーシートで研究内容を書くことは、理系の就活生にとって必ず通る道です。理系の学生は、普段から大学や学会で研究内容を発表する機会があるものですが、エントリーシートで研究内容を紹介する場合、研究発表と同じ内容では難しすぎますし、伝わるエントリーシートになりません。今回は、エントリーシートで研究内容を書くコツと、見逃しやすい注意点を見ていきます。
企業がESで研究内容を聞くことの意味
そもそも、企業はエントリーシートでなぜ研究内容を聞くのでしょうか。答えは、企業によってさまざまです。研究職や技術職の場合、研究内容をきちんと見て、類似の研究をしている人を集団面接で同じグループにして、面接官もその内容に合わせて変わる、というような「研究内容重視型」の企業もあれば、研究内容を理系学生の学生生活の本質的な部分と考え、内容は参考程度でその努力を知りたい「プロセス・考え方重視型」の企業もあります。
ほとんどの場合、たとえ研究職に付いたとしても大学の頃の研究をそのまま企業で続けることはできません。食品メーカーなどは特に、ほぼ100%の人が学生時代と関係のない研究をすることになります。そういった企業は、「プロセス・考え方重視型」が多く、研究内容のジャンルがある程度絞られていて、採用人数がごく少ないような研究職はどちらかというと「研究内容重視型」が多いです。
文字数の制限や設問の文面から「内容」を詳しくかくべきなのか、「エピソード」を詳しく書くべきなのかはなんとなく判断できますが、自分の志望する企業がどちらなのかを、説明会などの企業研究で把握しておくことが大切です。
【ケース別】ESでの研究内容の書き方
前の章でも述べたとおり、エントリーシートの研究内容は時と場合によって書き方がかわります。すべてを網羅できるわけでなありませんが、今回は3つのパターンに分けてそれぞれどのように書くべきなのか、見ていきます。
1【研究職など】研究内容がある程度絞られる場合
エントリーシートの制限文字数が多かったり(例えば800-1000字以上)、図を貼ることが許されていたりする場合は「研究内容」を詳しく書く必要があります。このようなタイプのエントリーシートは、文系の人事担当だけでなく、実際の研究職の社員や理系専門に人事を担当している社員が読むことが多いため、具体的に書く方が良いです。細かい固有名詞などは記号やアルファベットで置き換えても構いませんので、自分がやっている研究を差支えのない範囲でなるべく詳しく書きましょう。
また、実験の結果わかったことを淡々と書くのではなく、その証明のために行った実験手法を具体的に明記することで、自分がどんな技術を持っているのかを読む側に伝えることができます。流れとしては、「研究テーマ→研究背景(なぜその分野に注目して研究しているのか、それがわかると何に貢献できるのかなど)→研究方法(実際におこなった実験手法について)→(今のところの)結果→今後の展望」といった具合に、起承転結を意識した読みやすいエントリーシートを心掛けましょう。
2【理系総合職など】自分の研究とはあまり関係がない職種の場合
エントリーシートの制限文字数が400~600文字程度で、他の質問と同列の扱いをされている研究内容の項目は、研究の内容を詳しく書くことは不可能ですよね。なので、「自分は何に興味を持って何を研究している」という研究背景の部分を文系にもわかりやすい文章で書き、文字数に余裕があれば現在出ている結果や今後やりたいことを書きましょう。「簡潔に説明してください」などの項目だった場合、内容に関してだらだらと説明するのは良くありません。
中には100字や200字で本当に簡潔に書かせるエントリーシートもありますので、自分の研究を短く説明する練習もしておきましょう。さまざまな文字数に対応できるように、200字・400字・600字・1000字の四種類はベースとなる文章をあらかじめ作っておくのがオススメです。
3【総合職など】文系職の場合
文系職のエントリーシートでも、理系学生の場合「学生時代に力を入れて勉強したことを教えてください」のような問いに対しては研究内容を答えることになります。この場合は、詳しい説明は一切必要ないので、どんな研究をしているのか、研究背景を中心に簡潔に書き、挫折したことやその挫折からどう立ち上がったかなど、プロセスの部分を重点的に書くようにしましょう。具体的な書き方は次の「エントリーシートで研究内容を書くコツ」で見ていきます。
ESで研究内容を書く時のコツ


エントリーシートで研究内容を書くにあたって、意識した方が書きやすくなるコツをいくつか紹介します。詳しく書くパターンと、簡潔に書くパターン、ふたつに分けて見ていきます。研究内容はコツを押さえれば、伝えなければならないことが基本的には決まっているので、かなりスラスラ書くことが出来ます。
《詳しい研究内容の紹介が求められている場合》
1難しい内容でも「文系の人も読む」つもりで書く
「エントリーシートでの研究内容は、時と場合によって書き方を変える」の「①研究内容がある程度絞られる研究職の場合」で述べたように、詳しく研究内容を書くタイプのエントリーシートは、文系の人事担当だけでなく、実際の研究職の社員や理系専門に人事を担当している社員が読むことが多いです。しかし、だからといって専門用語だらけのエントリーシートにしていいわけでは決してありません。たとえ同じ理系でも、専門分野が違えば専門用語は理解できませんし、文系の人事も目を通すはずです。「このくらいわかるだろう」と思わず、何も知らない人が読んでわかる文章にすることを必ず心掛けましょう。親や文系の友達など、自分の研究を知らない人に一度読んでもらうことが大切です。
2研究の目的や今後の展望をしっかり書く
何をやったかだけが羅列されたエントリーシートは読みにくいですし、「目的」を飛ばして急に結果が出てくるとせっかくの成果の意義が読んでいる方に伝わりません。なんのための研究で、自分が出した結果がどれだけ意味のあるものなのか、そこを伝えられる能力もエントリーシートでは示すことができるのです。研究の内容を話すときは必ず結果以上に「研究背景」の部分に文字数を使いましょう。
また、今の結果がどの程度のもので、今後どうするつもりなのかというプランがしっかり立てられているかどうかというのも見られているポイントです。面接で聞かれたときにスムーズに話が広がるように、エントリーシートにも今後の展望について少し触れると良いです。
3企業で活かせる技術や能力をアピールしながら書く
自分が企業でも使いそうな実験手法や技術を身に着けているならば、それはエントリーシートでアピールすべきポイントです。特に詳しく研究内容を書く場合は、用いた手法も具体的に書くと良いです。また、論理的に考えられる能力や結果をただ受け止めるのではなくそこから考察する能力などは、理系の研究室でこそ育つ強みでもあります。そのあたりも、自分の得意とするところを明確にしてアピールしながらエントリーシートを書けると良いでしょう。
《詳しい研究内容の紹介が求められない場合》
4とにかく分かりやすく、かみ砕いて書く
「簡潔に」「簡単に」説明してください、のような質問の場合、文字数が少なくなるのでかみ砕いて説明するのはなかなか大変です。だからといって、専門用語を並べた呪文では意味がありません。制限文字数が少なく、簡単な内容しか書けない場合、エントリーシートの段階では研究職の社員は読まない可能性が高いので、誰にでもわかりやすい文章になるように何度も読み返し、必ず何も知らない人に読んでもらうようにしましょう。
5どう頑張ったかなど「過程」に重きを置く
特に文系職や総合職などの研究とあまり関係のない職種を受ける場合、エントリーシートでは研究の内容はまったく重要ではありません。その場合どういった研究をしているのか詳しく書くのではなく、
- どういうきっかけ・モチベーションで(何に興味があるから)研究しているのか
- 挫折したこと・大変だったことは何か
- 学んだこと・ためになったことなど今後の人生に活かしていけそうな経験は何か
- それを踏まえて入社出来たらこの経験をどう活かしたいか
など、研究内容ではなく「ためになった経験」として研究のエピソードを書く形にしましょう。
ESで研究内容を書く時の注意点
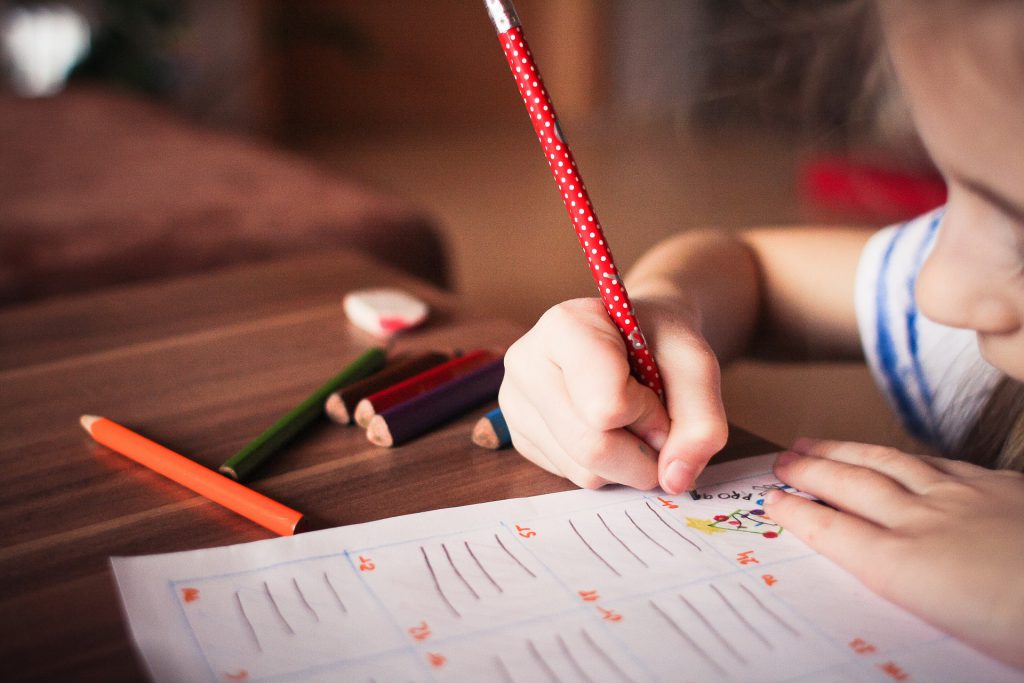
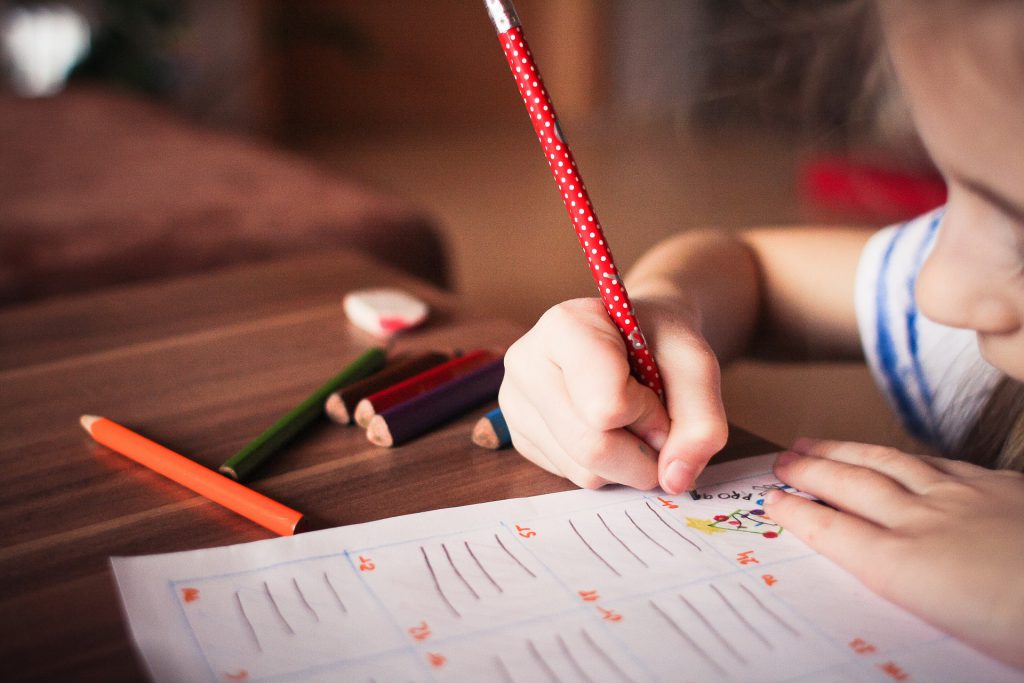
理系学生にとって研究内容を人に説明するのは慣れていることではありますが、それはいつも教授や他の研究室の友達など、自分の研究背景をなんとなく知っている人に対して行うことが多いですよね。そうではなく、何も知らない人が聞いてわかる研究内容にするための注意点をいくつか挙げていきます。
研究発表で使っている紹介をそのまま使わない
エントリーシートで研究内容を書く場合、たとえ文字数が多くて相当詳しくかけそうな場合だったとしても、大学で研究者向けに使っている研究概要をそのまま使ってしまうと、わかりにくい文章になりがちです。ベースとして参考にするのはもちろん構いませんが、段落の構成や言葉の説明の部分は考え直してわかりやすく書き換えましょう。研究発表などで使う研究概要で暗黙の了解的に省略してしまっている説明も、エントリーシートでは省かないで書きましょう。
添削は研究者よりも文系の人に
書いた文章を自分で読み返したら、人に見てもらうのはエントリーシートの基本です。
理系の学生は、教授に添削を頼むことも多々あります。それはそれで添削してもらってかまいませんが、その後に、必ず何も知らない、出来れば大学生でもない親や兄弟、文系の友達に読んでもらいましょう。教授の添削は、どうしても研究発表向けの思考でされてしまうため、必ずしもエントリーシートにふさわしい内容にはなりません。
許可されている場合は模式図なども入れて
しっかり研究内容を把握したいと思っている企業は、エントリーシート(ES)に図を添付することが許されていることがあります。その場合、図は必ず入れましょう。研究内容というのは、視覚的な情報があればあるほど理解しやすいです。できれば、結果のグラフなどではなく、自作の模式図のような図で研究の流れや内容がわかるものにすると、一つの画像で多くの情報をわかってもらうことができます。図の枚数は決まっていることが多いので、指定の枚数内で重要な図をまとめるようにしましょう。
【例文】ESで研究内容を伝えよう!
上記でご紹介したポイントをふまえつつ、さっそく研究内容を伝えるESを書いてみましょう。以下ではESに研究内容を書いた例文をご紹介します。ぜひ自分の書いたものと比べてたりして参考にしてみてくださいね。
研究過程では他の遺伝子と比較して進めるため、いかに効率的な検証手法を取れるかを常に考えることを意識していました。その結果、実験のスケジューリングやタスク管理能力が身に付き、また複数の学生との議論を通してコミニュケーションの大切さを実感することができました。
質の良い食事で幅広い年齢層の健康促進を目指すだけではなく、食を通してより良いコミニュケーションを取る事を理念としている貴社に魅力を感じ、志望致しました。」
まとめ
いかがでしたか?エントリーシートで研究内容を紹介するのは、研究発表とは勝手が違って戸惑うこともあるかもしれません。しかし、さまざまな立場の人に読んでもらうことで、わかりやすい文章になっているかどうかをしっかり確認すれば大丈夫です。エントリーシートで研究内容をわかりやすく紹介して、自分の研究内容に興味を持ってくれる企業を見つけましょう。
またESで研究内容を上手に伝える自信がない方はメンターズがオススメです。就活を勝ち残った現役の社会人がES添削から内定までをサポートします。





コメント