就活の中でも重要な評価を受ける「作文」について、失敗しやすい書き方と注意点を解説します。就活作文で出やすい出題例と、回答の例文の一部も、あわせて紹介します。
作文能力は就活で重要!書き方を覚えておこう
就活作文は、企業が応募者の能力や人格を見極めるのに使われます。
文章から、ビジネスで重要になるコミュニケーション能力や情報伝達能力を測れることがあるため、作文能力は就活生の必須技能ともいえます。
就活作文の書き方の注意点をおさえ、ビジネスでも通じる文章が書けるようになりましょう。
就活作文で注意すべき書き方8選


就活作文には、大きくわけて8つの注意点があります。
注意点は、就活作文以外の場面でも多く役立つ、「読みやすい文章の基本」の形です。
ぜひ覚えて活用できるようにしましょう。
- 注意点1: 文字数を意識する
- 注意点2: タイトルから逸脱しない
- 注意点3: 「ですます調」で記述する
- 注意点4: 1文は読みやすい長さにする
- 注意点5: 1文で主張する内容は1つにする
- 注意点6: SDS法で構成する
- 注意点7: 誤字脱字に注意する
- 注意点8: 伝えたいことを明確にする
注意点1: 文字数を意識する


就活作文で、出題の中に文字数の指定がある場合、指示が「○○文字以上」「○○文字程度」かによって理想の文字数が変わります。
例えば◯◯文字以上は指定文字数必達であり、300字以上なら301文字が最低ラインになります。
ただし、300文字以上ならいくらでも書いていいわけではなく、指定文字数を大きく上回る長文は逆に悪い印象になってしまうこともあります。
指定された字数を二割以上、上回ることがないようにすることが理想です。
◯◯文字程度や◯◯文字以内という指示では、指定文字数の90%以上の作文が目安です。
300字の90%なら270字のため、280か290文字ほどで収められるのが理想になります。
注意点2: タイトルから逸脱しない
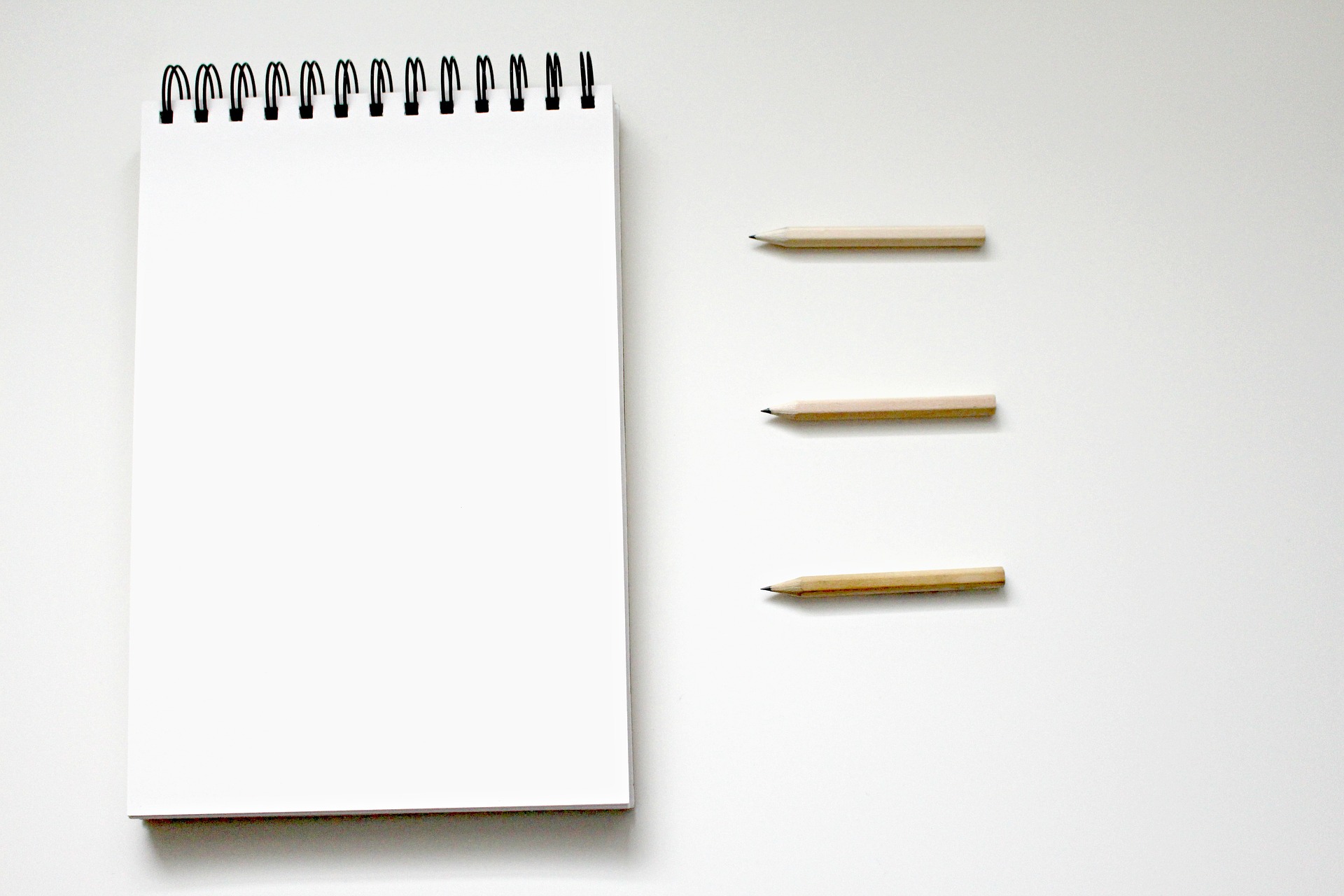
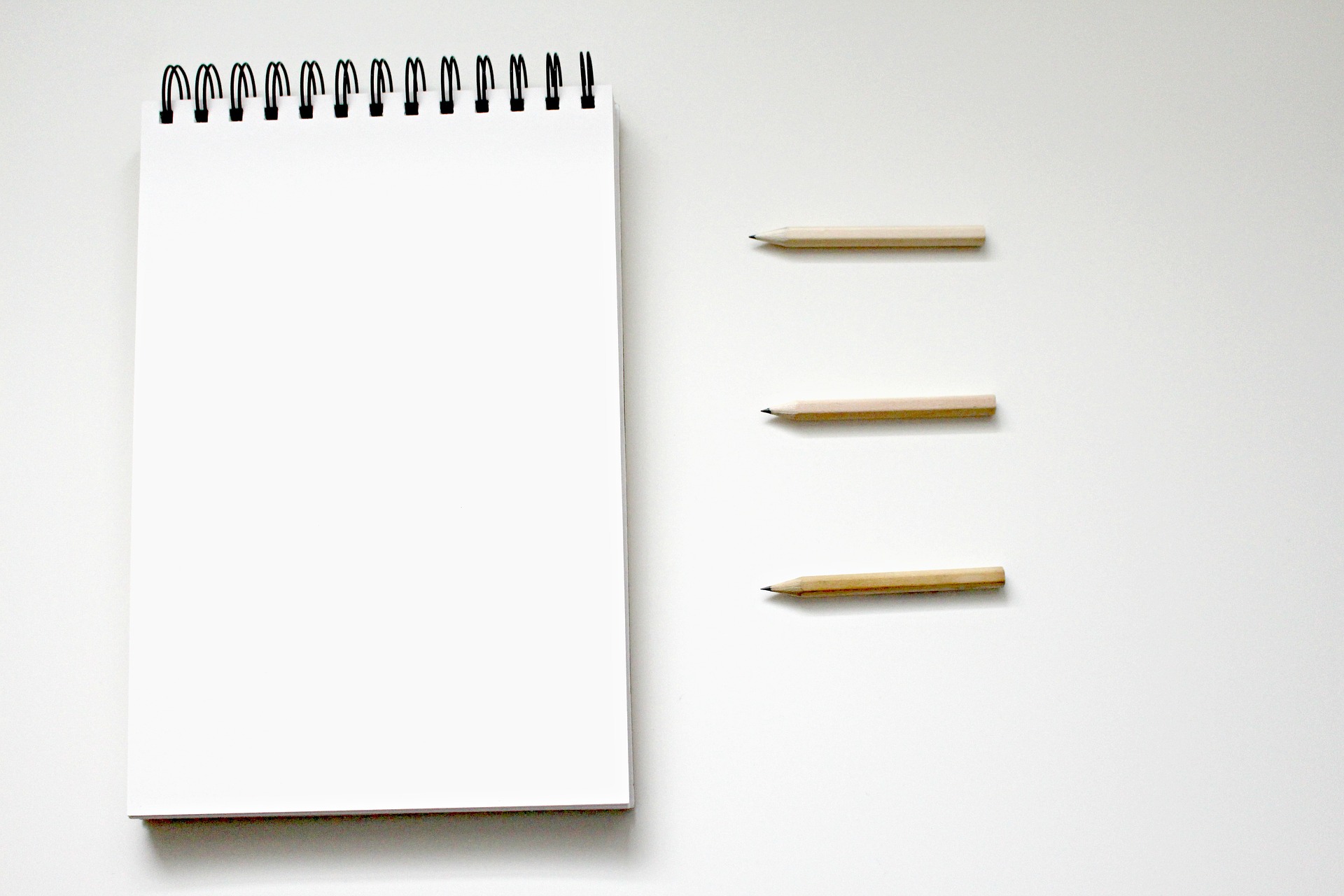
作文を書くときに重要なのは、最初に決めた作文のタイトルから逸脱しないようにすることです。
タイトルと違った内容をあえて書く技法もありますが、「読みやすい文章の基本」ではタイトル通りの文章が望ましいです。
就活作文は読みやすい文章にすることが大切なので、タイトル通りの文章を作成しましょう。
もしタイトルから文章が逸れてしまう人は、先に全体の文章を作ってから、最期に作文に合ったタイトルを考える方法でも大丈夫です。
注意点3: 「ですます調」で記述する


就活作文では、特に指定が無い場合は「です」「ます」の口調を用います。
就活作文から、コミュニケーション能力の高さや、字頭の良さなどの採点が成されることもあります。
敬語が正しく使えている、文章がまとまっている、設問に対する答えが出ている、なども大事な評価基準になります。
目上の人へ提出する書類、という観点からも、就活作文は「ですます調」にしましょう。
注意点4: 1文は読みやすい長さにする


読みやすさが重要な就活作文では、1文の長さにも注意が必要です。
作文は1文が長過ぎても、短すぎる文章の連続でも、読みづらくなります。読みやすい文章を書くときに重要なのは、読店「、」の位置と個数です。
読点がない文章は、息継ぎの間がなく読みづらいものになってしまいます。読点が多すぎると、途切れ途切れで息の詰まる文章になります。
読みやすい文章を心掛けるべき就活作文では、1文に読点は1個、多くても2個までにしましょう。
読点が1・2個の文章なら、長過ぎることも短すぎることもなくなるはずです。
注意点5: 1文で主張する内容は1つにする
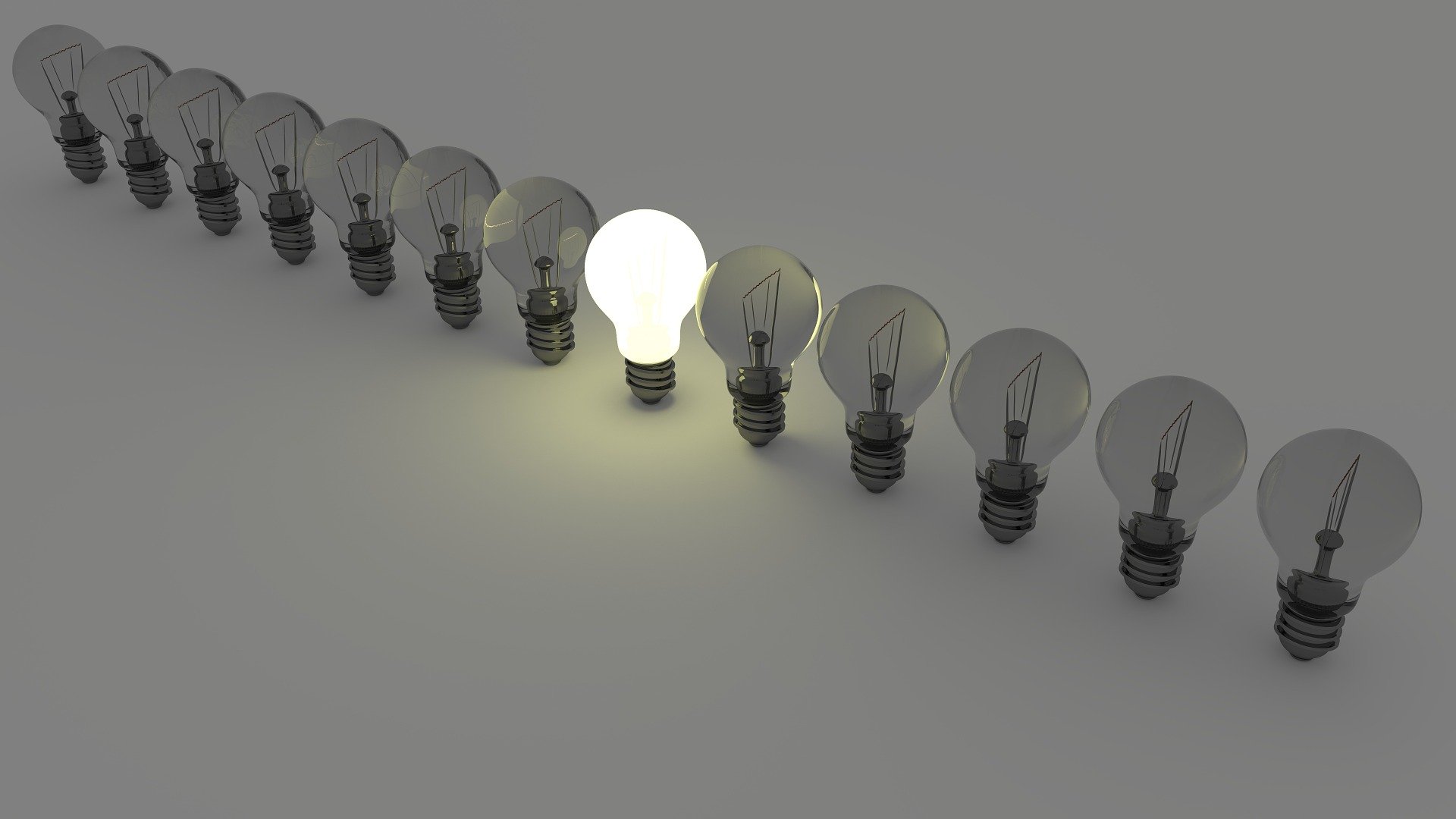
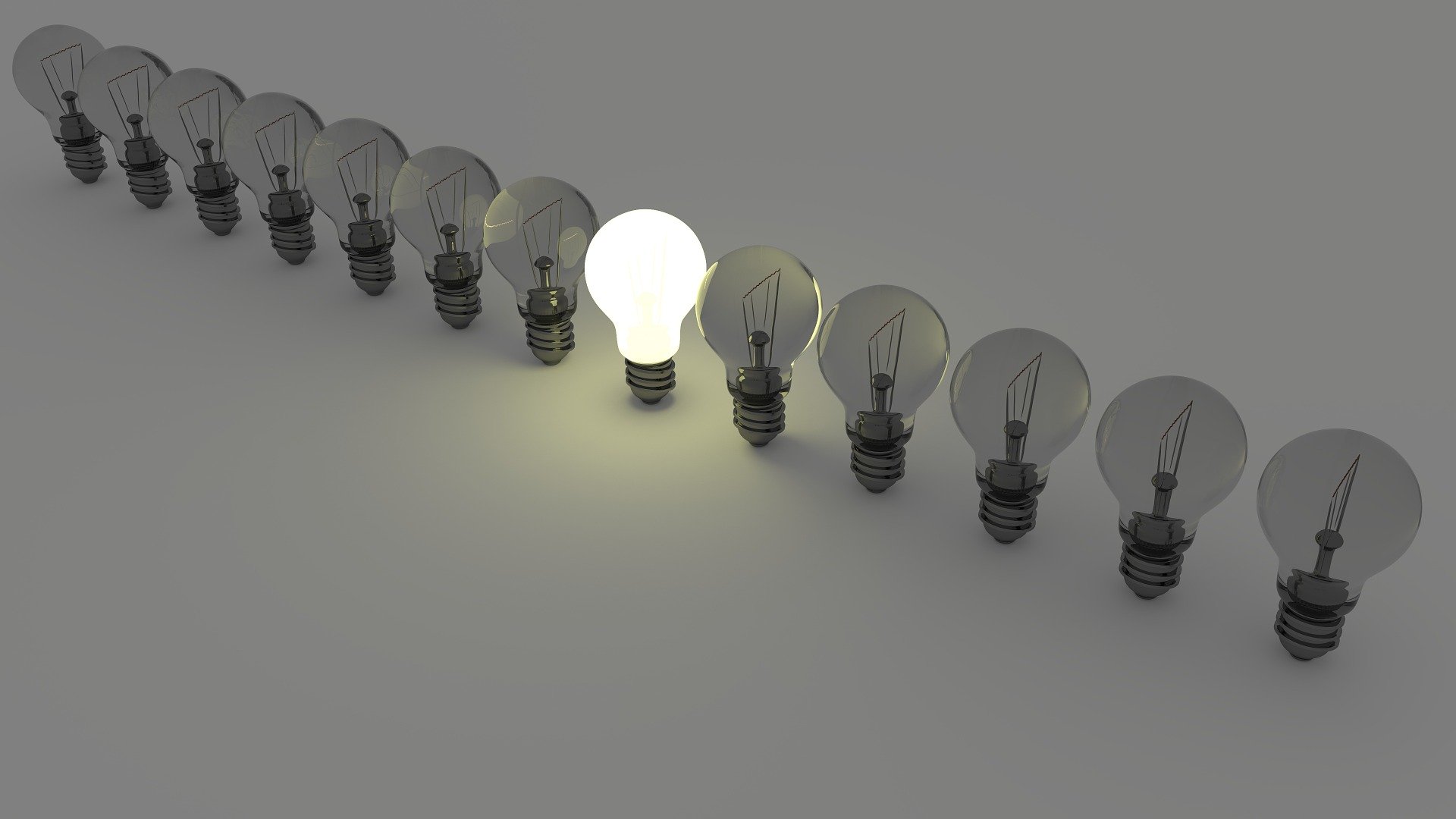
1つの文章の中に2つ以上の主張を混ぜると、冗長で締まりのない文章になってしまいます。
せっかくの主張も、印象がぼやけてしまう場合があります。
2つ以上の主張を1文に含めると読みにくくなるため、「1つの文章には1つの主張」を徹底しましょう。
2つの主張をしたいときは、文章を2つに分けるようにしましょう。
注意点6: SDS法で構成する
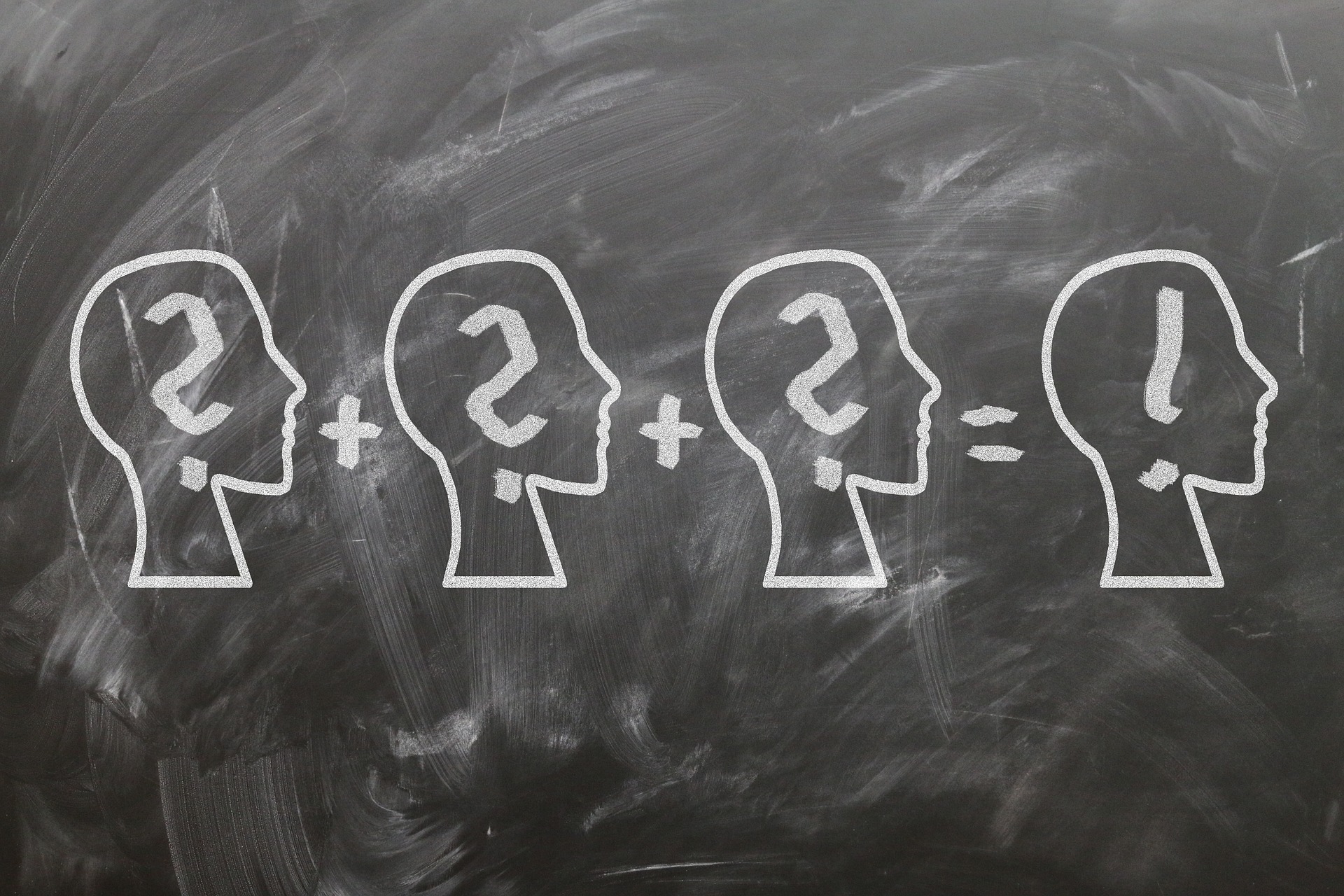
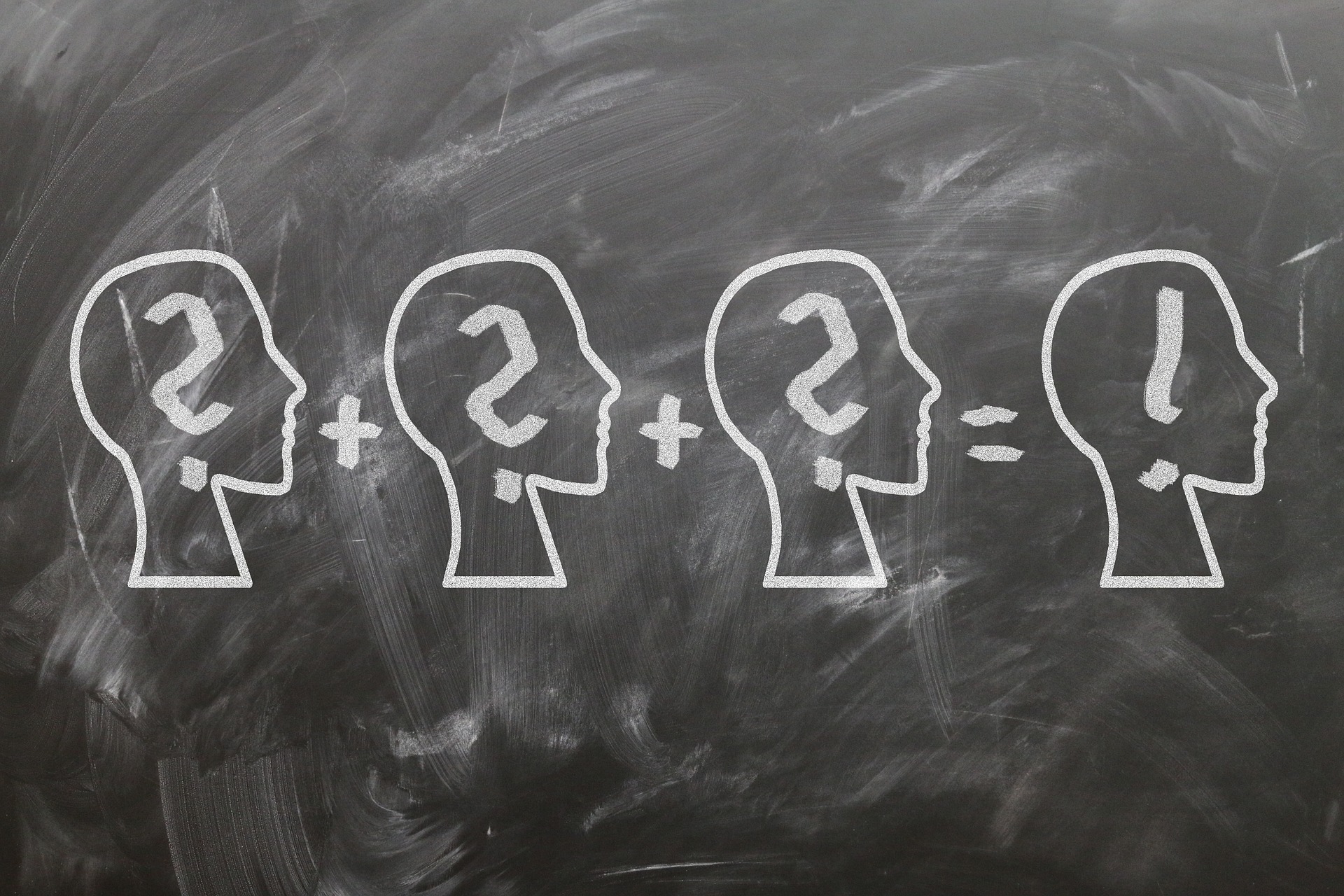
就活作文での文章の形は、SDS法が望ましいです。
SDSとは「Summary・Details・Summary」の略称で、それぞれ「概要・詳細・要約」のような意味を持ちます。
就活作文でSDS法を使う場合は、まず「何についての文章か、簡潔に概要を説明する」「内容について書く」「最期に、何についての文章だったか内容をまとめる」という流れになります。
レポートを書くことが多い人は、「序論・本論・結論」と似た流れになると想像してください。
SDS法を自在に使えるのはプレゼンテーション能力にも直結するため、深く理解して様々なものに応用できるようにすると良いでしょう。
注意点7: 誤字脱字に注意する


就活作文では、誤字脱字に細心の注意が必要です。
漢字の間違いや接続詞が抜けている、などは誤字脱字でよく起こります。
自分一人では誤字脱字が気づきにくいため、他の人に読んでもらう・チェックツールを使うなどして、丹念に見直しましょう。
読み方が同じのため間違えやすい、「ず・づ」「は・わ」などのひらがなや、「測る・計る」などの漢字の使い分けも要注意です。
また、「御社」と「貴社」も間違えて使わないようにしましょう。
話ことばが「御社」で、書き言葉は「貴社」になります。
注意点8: 伝えたいことを明確にする
![]()
![]()
就活作文では、自分の伝えたいことを明確に表す必要があります。
遠回しな比喩や暗喩は使わずに、伝えたいことを素直に書きましょう。
伝えたいことの印象を変えたい場合は、比喩表現を使わず、言葉を言い換えることで印象を操作しましょう。
就活作文によくあるテーマと解答例文3選


就活作文によくあるテーマを3つ、回答の例文や作成のポイントと共に紹介します。
面接などでは提出した作文についての言及がある場合も多いので、自分が書いた文章の内容はきちんと把握しておきましょう。
仕事とは何か


「仕事とは何か」という設問があった場合、まずは企業がなぜこの質問をしたのか、想像してみましょう。
企業は就活作文を通して、応募者の人間性を測りたいと思っている場合がほとんどです。
「仕事とは何か」の設問に、どのように答えるかで、応募者の価値観や、企業との相性を確認しようとしていることが多いです。
「仕事とは何か」は、働くことの本質に深く関係する問答になるため、慎重に考えをまとめましょう。
就活作文を書くとき、「仕事って何だろう?」から入るのではなく、「自分にとって、仕事をするうえで最も重要なものはなんだろう?」と考えてみましょう。
このとき、「自分の希望する待遇はなんだろう」と混同せずにアイデアを出していきましょう。
「週休二日制」「残業手当有」などは、自分にとって仕事をするうえで最も重要なことではなく、仕事をするうえでの待遇の希望になってしまいます。
仕事をするうえで最も重要なことには、「自分が業界・業種を目指そうと思った瞬間は何だったか」の中に答えが見つかる場合が多いです。
また、作文の流れはSDS法を用い、「仕事とは何かを述べる」「なぜそう考えたか、自分の経験をもとにした本論を述べる」「仕事とは何かの結論を述べる」というように書きましょう。
一例として、「私にとって仕事とは、心を揺さぶる出来事を起こし、人を幸福な気持ちにさせる手段の一つです。私は学生時代に、(自分の経験に基づくエピソードを具体的に入れる)を経験しました。これは生涯忘れられない、特別な瞬間となっています。貴社の事業を通して、人々の記憶に幸せな記憶が強く残る、特別な一日をつくり出していきたいと考えます」などが挙げられます。
もし自分の中でどうしても仕事への価値観が定まらない人は、活き活きと働いている人に、やりがいや楽しみ・喜びは何かを質問すると、ヒントを得られることもあります。
「週休二日」「高給」「残業手当有」など待遇希の望以外に就活する理由が見つからない人は、給料や待遇が最重要事項なら必ずしもまっとうな職業に就く必要はないため、就活でよくある「うちの会社じゃなくてもよくない?」の問題に上手に切り返せなくなります。
「じゃあ、とにかく犯罪にならないけど忙しくなくて大変じゃない高給な仕事がしたい」場合は、「ビジネスの分野で、どこよりも上を目指していきたです。貴社はビジネスの中でもトップクラスの業績があり、ここでなら自分の夢を叶えるヒントを得られ、希望ある将来を感じられる仕事ができるはずだと考えます」などと言い換えられます。
本当の動機が作文に書けるほど立派なものじゃない人は、「嘘」にならない程度に、印象の良い言葉に換えて伝えましょう。
学生時代に学んだこと


学生時代に学んだことに対する就活作文は、3つの手順にわけると書きやすくなります。
まずは、「学生時代に何を学んだのかの序論」を述べ、「具体的な勉学の内容と、学んだ結果」「勉学を通して何を得たのか、今後どう生かせるか、自分の感想と結論」という流れで書きましょう。
一例として、「私が学生時代に学んだことは、仲間と力を合わせて物事を成し遂げる重要性です。私は授業で○○を先行しており、発表を通して仲間と意見交換を繰り返しました。最初は私も含め仲間たちの意見も消極的でしたが、発表を重ねるにつれ、仲間からも思いもよらない視点からのアドバイスをもらえるようになり、自分ひとりの力では成し得なかった、ハイクオリティな発表ができるようになりました。自分の発言が仲間の発表の質を上げることに役立ったときもあり、互いの成長に喜びを感じました。私たちは、自発性のある活発な意見交換で、ひとりひとりの力を高め合うことが出来ると考えます。積極的な発言と自発的な行動が及ぼす影響の重要性を知ったので、これからも、周りに意見を求めながら自分は仲間に何ができるかも考え続けたいと思います」というのが挙げられます。
学んだことと学びから得たことは、十人十色です。
自分の経験をもとにしたエピソードを、ポジティブな印象になるように組み立てていきましょう。
テーマ3: 志望動機


就活作文には、志望動機を述べる設問がある場合も多いです。
志望動機に関しては、自分の希望する業種・職種についての動機を明確かつ具体的に述べましょう。
志望動機は、「なぜこの業種・業界を目指したのかの自分の体験や感情」と、「なぜこの会社を選んだかの他社との比較」の2点が伝えられていることが理想です。
志望動機の作文は、独自の経験や感情に基づく作文が好まれます。
就活作文は「自分のことを、自分の言葉で書く」ことが重要なため、コピペは絶対NGです。幼い頃に抱いた夢の話や、仕事への期待感など、動機はオリジナルの理由を考えましょう。
なぜこの会社を選んだかについては、「自分が目指した業界の理想像が、貴社の取り組みの中にあると感じました。貴社が掲げている理念でもある○○は、自分の志と同じであると考えます」など、応募先の会社の持つ理念や方針、仕事への取組みの姿勢にも言及すると良いでしょう。
社長挨拶や上役の紹介がHP上に載っている会社もあり、そこからも、企業が重要視している理念や指針を把握するヒントを得られるので、目を通しておきましょう。
自分と応募先企業、双方のリサーチがきちんとできていれば、悪い印象の内容にはなりにくいです。
ただし、給料や待遇の話は持ち出さないようにしましょう。言及する場合は、直接的表現を避けて「社員を大切にしている」などと言い換えましょう。
作文の流れはSDS法を用い、「なぜ会社を選んだかを述べる」「なぜそう考えたか、自分の経験をもとにした本論を述べる」「会社を選んだ結論を述べる」というように書きましょう。
就活作文を書くときのポイントを押さえておこう!


就活作文を書くときには、読みやすい文章を書く以外にも、3つの重要なポイントがあります。
就活作文は、企業に自分をアピールする好機です。
ポイントをおさえた文章で、良い印象を残せるようにしましょう。
- ポイント1: 問題の意図を把握して明確に解答する
- ポイント2: 簡潔・明快に記述する
- ポイント3: 応募先企業の価値観にマッチさせる
ポイント1: 問題の意図を把握して明確に解答する


就活作文では、出された問題の意図を正確に読み取り、回答を明らかにすることが大切です。
例えば、学生時代に打ち込んだことの設問に、志望動機の回答を混ぜ込んではいけません。
学生時代に打ち込んだことの設問には、そのテーマに沿った内容のみを主張するようにしましょう。
ポイント2: 簡潔・明快に記述する


就活作文では、句読点の数・誤字脱字などの「読みやすい文章のポイント」以外にも、主張を簡潔・明快にするというのが重要になります。
設問に対する答えは、引き延ばしたり後回しにしたりせず、SDS法を意識した明確な文章にしましょう。
応募者の多い大企業などは、就活生ひとりひとりの作文を、じっくり時間を割いて読めないこともあります。
少ない時間の中で読まれる文章は、読みやすいことも大切ですが、主張が簡潔で明快であることも非常に重要です。
ポイント3: 応募先企業の価値観にマッチさせる


就活作文では、応募先企業の価値観に反さないような文章が大切です。
企業にはそれぞれ、抱いている理念や掲げている指針があります。
応募先企業がどのような理念・指針に基づいて活動しているのか、その価値観を把握し、就活作文の文章を適切に言い換えましょう。
就活生必見!作文を書くときの5つの手順をチェック


作文には、「文章が書きやすい手順」があります。
就活作文を書くときは、ひとつひとつの段階を踏んで、じっくりと文章を作成していきましょう。
就活作文が書きやすくなる手順を、5つにわけて紹介していきます。
手順1: 伝えるべきポイントを決める


まずは、就活作文で伝えたいポイントを決めましょう。
伝えたいポイントは作文全体の主軸となる重要なテーマなので、要点をしっかり定めます。
これからどんな内容について書きたいのか、作文を通して何を伝えたいのかを、しっかりと意識しましょう。
このとき、自分の伝えたいポイントが、企業からの設問に明確に答えらているかどうかも考えましょう。
もし設問から外れた回答になるかもしれない、と思ったら、書き出す前に伝えたいポイントを変えましょう。
手順2: 概要を序論として記載する


就活作文の書き方では、SDS法の「概要・詳細・要約」を用います。
まずは、導入部分である概要を書き出しましょう。
導入の部分は、就活作文の概要を序論として伝えます。
例えば学生時代に打ち込んだことなら、「私が学生時代に打ち込んだことは○○です」というように、自分がこれからどんな内容について書くのかを明確にする部分になります。
手順3: 本論で詳しく説明する
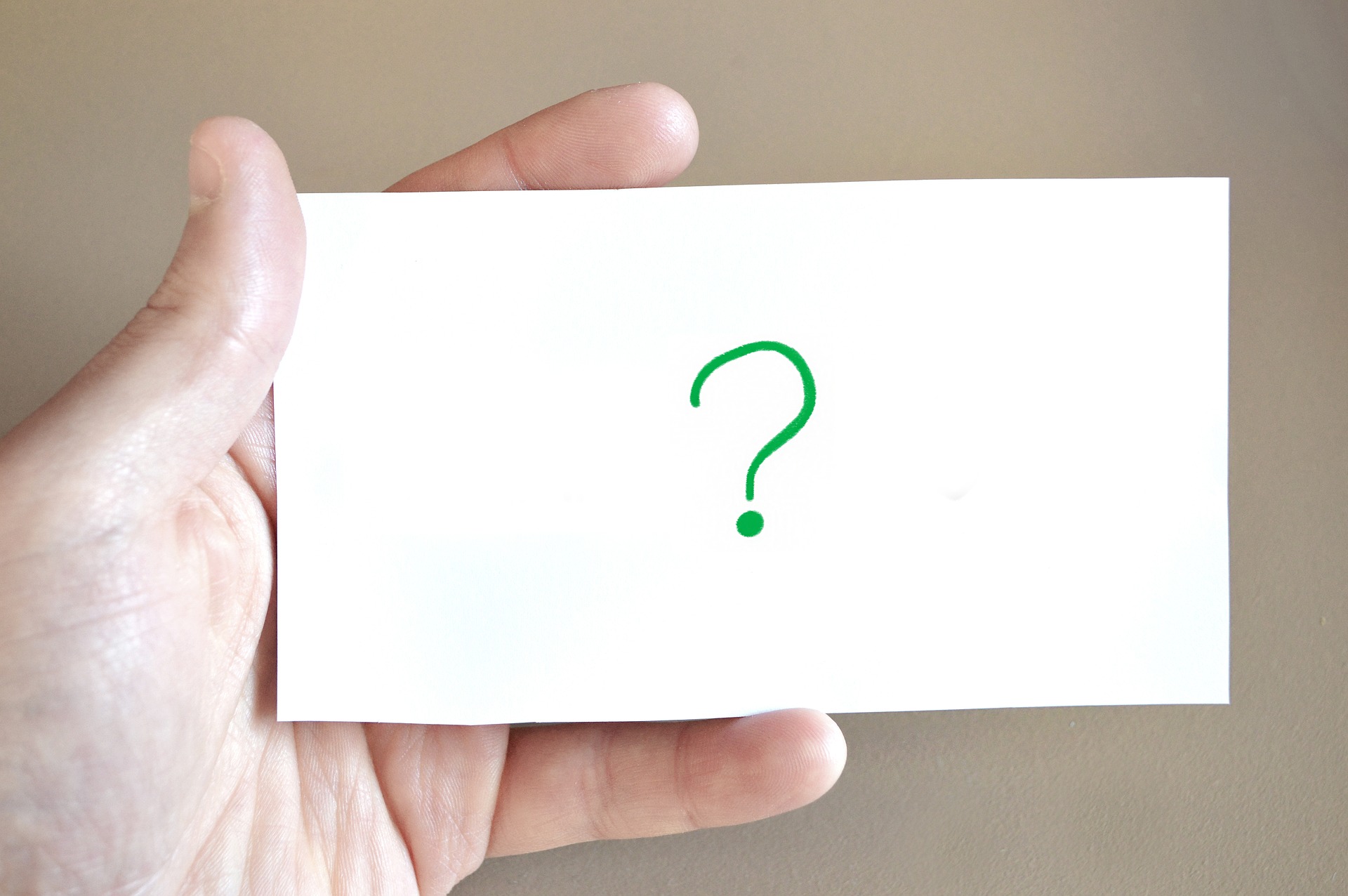
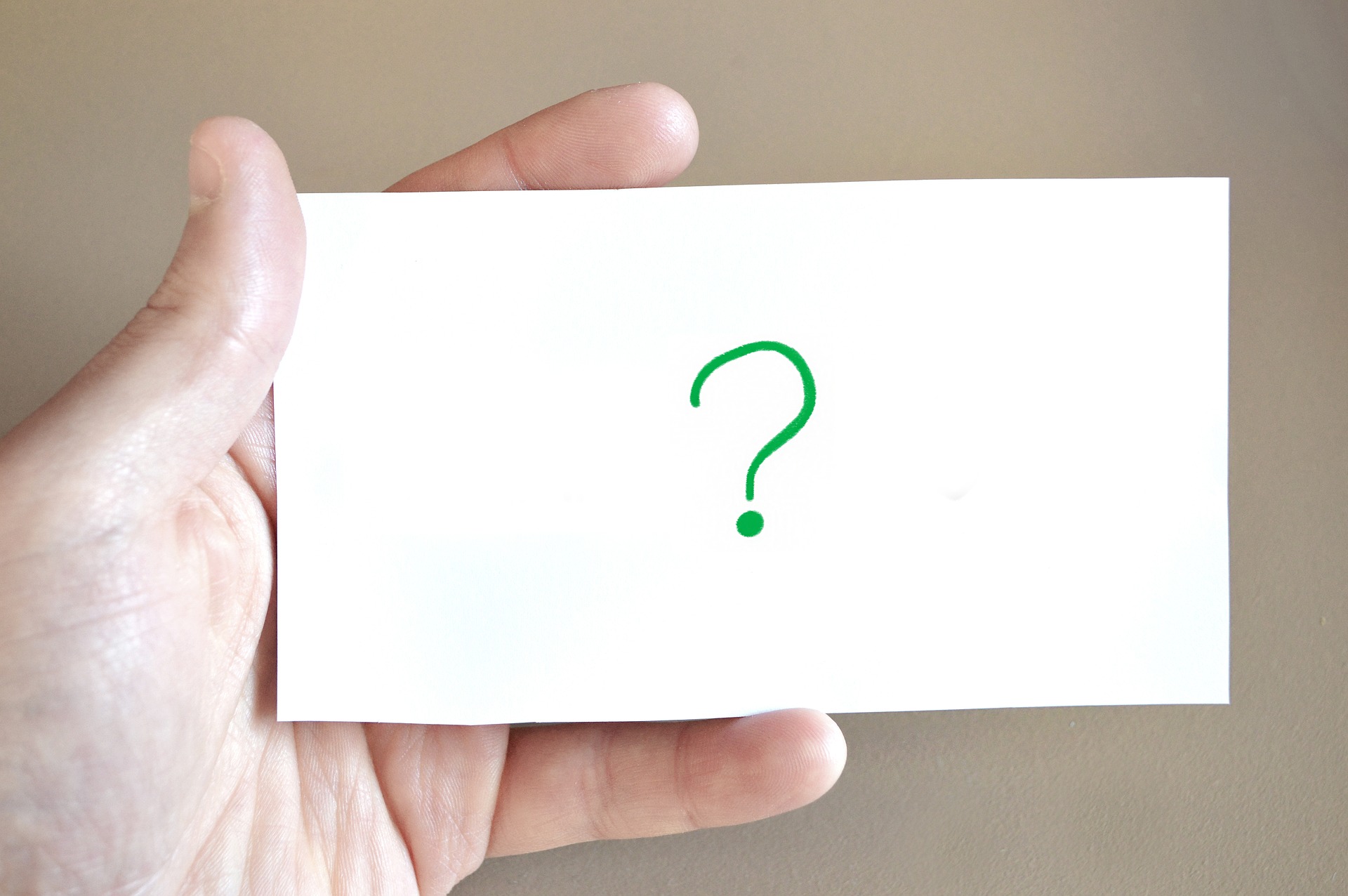
導入部分で序論を述べたあとは、SDS法の「概要・詳細・要約」における詳細部分に入ります。
ここでは、就活作文の本論となる内容を書きます。
導入部分で明記したポイントに沿った詳細内容を、1文の長さや句読点などに配慮した、読みやすい文章を心掛けながら述べていきましょう。
手順4: 結論でテーマに対する回答を明確に記述する


本論が終わったら結論を仕上げます。
SDS法における最後の一段階である、「要約」を書きましょう。
結論では、テーマに対する回答を明確に記述する必要があります。
学生時代に打ち込んだことの設問へ回答した作文なら、「この経験を通して、○○の力が身についたと感じます」など、経験を通して得た知見や身についた能力などを述べる部分が「結論」です。
手順5: 作文全体に一貫性があるかを読み直して確認する


作文が書き終わったら、筆を置いて全体を見直しましょう。
自分の書いた文章に一貫性があるか、テーマがふらついていないか、設問に沿った回答になっているかなどをチェックします。
文章の内容を見直したら、誤字脱字がないか、細部も念入りに見直しましょう。
就活作文の企業側の目的について


就活作文は「企業側は、問題を通してどんなことが知りたいのか」まで想像を働かせながら文章を考えると、より良い回答につなげ易いです。
就活作文を出す企業側の目的を想像して、自分の文章に生かしましょう。
- 応募者の人間性を知りたい
- 文章力を測りたい
- 適正があるかを判断したい
応募者の人間性を知りたい


企業が就活作文の提出をお願いするのは、応募者の人間性を計ろうとしている場合が多いです。
今はネットで参考例文が多く出回っているので、その文章を少し手直ししたままコピペしてくる就活生も多くなっています。
企業側は、コピペした作文を提出してきた就活生を、基本的に採用しません。
そのような就活生の人間性などを、就活作文を通して採点しています。
文章力を測りたい


就活作文を通して、ビジネス文章への適性があるかどうかの文章力を測りたい、という企業もあります。
社会に出て働くと、ビジネス文章を書く能力が必須になります。
文章を書く能力が低いと、円滑なコミュニケーションや正確な情報伝達ができなくなり、業務に支障が出てきます。
簡潔で明快な文章が書ける人かどうか、力量を見極めるために就活作文をお願いしていることが多いです。
適正があるかを判断したい


企業は、社会に適性があるかどうかも、就活作文を通して判断しようとしています。
与えられた指示ができるか(指定文字数に沿ったか)、質問を理解できる程度のコミュニケーション能力があるか(設問の意図がきちんと汲み取られているか)、自分の発言に責任があるか(回答にブレがないか)、などが就活作文から採点されます。
就活において作文能力は重要!文章力を向上させておこう


就活において作文能力は重要な採点ポイントです。
SDS法を心得た文章で、要点を簡潔に伝えられる文章を作成できるようにし、就活後の社会でも生かしていきましょう。





コメント