就活生の皆さん、グループディスカッション のテーマは把握できていますか?志望する企業が大手企業だった場合、選考の一環でグループディスカッション(GD)をすることがあります。グループディスカッション(GD)とは、複数の人間でチームを組み、提示されたテーマについて議論をする選考です。企業側は議論を行う学生一人一人を観察し、次の選考に進む学生を選びます。
学生は、グループディスカッション(GD)を苦手とする傾向にあります。理由としては、「何を基準に合否が決まるのかが分からない」「アピールの方法がわからない」「初対面の学生とコミュニケーションをとるのが苦手」が挙げられます。
そこで今回は、グループディスカッション(GD)でよく出されるテーマとそれに対する対策を紹介します。パターンさえ読めれば、グループディスカッション(GD)で自分の存在を企業側にアピールできるので、興味のある方はぜひご覧ください。
グループディスカッションでテーマに沿って学生に議論させる理由とは?
グループディスカッション(GD)は、すべての企業で行われる選考ではありません。規模の大きい大企業で、書類選考を突破した学生に対する最初の選考として行われるのがほとんどです。
大企業は様々な理由から、グループディスカッション(GD)を行い学生を選別したい考えています。まずはグループディスカッション(GD)を大企業が実施する理由を知り、選考に対する理解を深めましょう。
ここでは企業がグループディスカッション(GD)を学生に行わせる理由を3つご紹介します。
①選考の負担を減らしたい
大企業がグループディスカッション(GD)選考を行う理由として、選考の負担を減らしたいことがあります。大企業の選考には数多くの学生が応募し、書類選考だけでも数は膨大。従来通り一人一人に面接を行っていては、人事担当に大きな負担がのしかかります。
そのため、グループディスカッション(GD)をまず行い、学生のふるい分けを行うのです。数人で組ませたチームを複数作れば、数十人の学生を一斉に選考することができます。多少大雑把な選考にはなりますが、グループディスカッション(GD)の後は一人一人面接でじっくり素質を確認すればいいのです。
なので、学生はグループディスカッション(GD)で自分を効果的にアピールする必要があります。ただでさえ多人数なうえ時間も限られているので、気を抜いているとあっという間に課題が終わって選考にも落ちた、ということになりかねません。
②学生のコミュニケーション能力を確認する
2つ目の理由として、学生のコミュニケーション能力を確かめたいという思惑があります。従来、コミュニケーション能力を確認するために面接が行われてきましたが、面接は一対一でのコミュニケーション能力しか確認できません。面接では雄弁でも、入社した後の集団のなかでは寡黙だったという例も珍しくありません。面接は対策されやすいので、決まり切った問答になりやすいという弱点もあります。
このような事情から、大企業はグループディスカッション(GD)で集団の中での学生のコミュニケーション能力を確認したいと思っています。初対面の学生同士で議論を行うので、事前に対策を練ることが難しく、素のコミュニケーション能力も出やすいです。
コミュニケーション能力はすぐには向上しないので、学生はグループディスカッションで合格するための対策を事前に考えましょう。グループディスカッション(GD)でどのような課題が出されるかはリサーチすることが可能です。出された課題に対してどのような議論を行うか、他の学生に対してどのように差をつけるかをイメージしておけば、ある程度有利に立ち回れます。
③学生の集団の中での役割を見る
グループディスカッション(GD)を行うことで、学生が集団の中でもどのような役割を果たしているのかを知ることができると考える企業もあります。
企業が求める人材の人物像は多種多様です。ある年はリーダーシップのある人材を、またある年は積極的に意見をだしてムードを盛り上げる人材を求めるなど、年によって求め人材が違う企業もいます。グループディスカッション(GD)課題ではリーダーを務める者、意見をまとめる者、問題点を指摘する者など学生の個性が見てくるので、企業が求める人物像とマッチしているかを見ることができるのです。
学生は、グループディスカッション(GD)では自分の個性を100%出せるようにしましょう。自分の個性にマッチしていなければ、無理やりリーダーを務める必要もありません。限られた時間の中で自分の特性を発揮できれば、企業側の人間の目に留まるはずです。
グループディスカッション (GD)で採用担当者が評価している基準を以下の記事に「詳しくまとめました。ぜひ参考にしてください。
グループディスカッションで頻出するテーマ
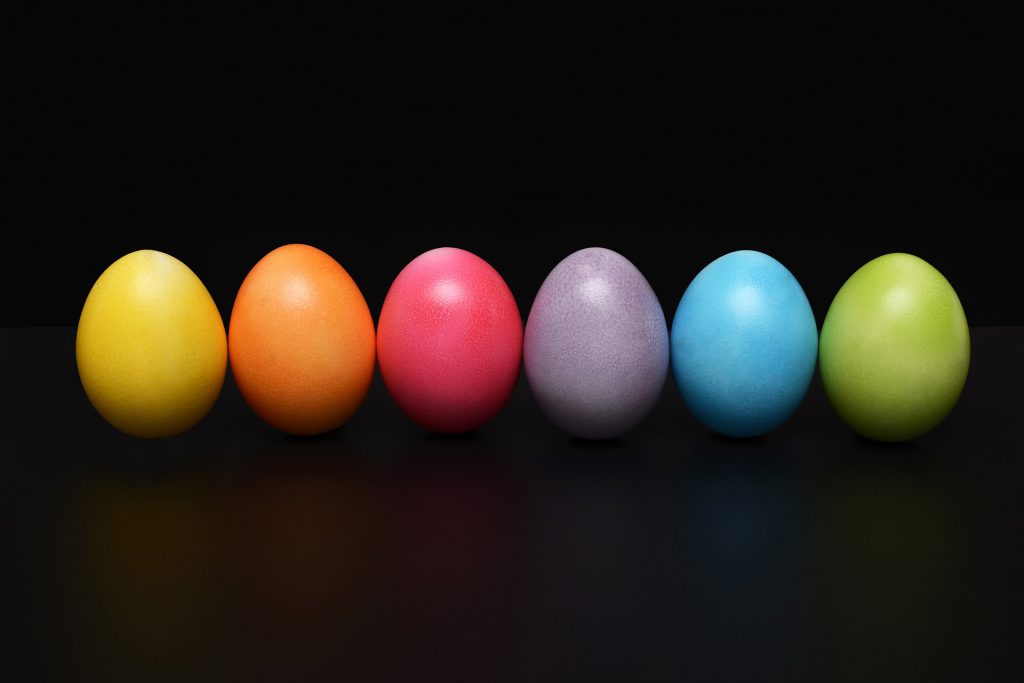
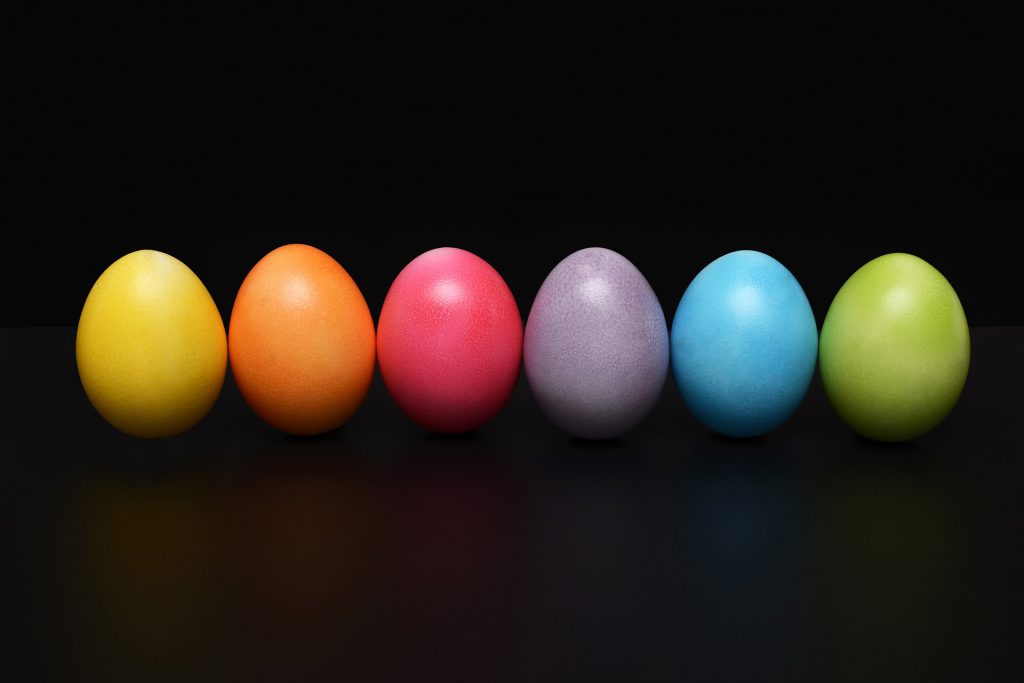
それでは、グループディスカッション(GD)でよくあるテーマを4つご紹介していきます。テーマ別の特徴を把握していれば、集団の中でも自分の良さをしっかりアピールすることができるでしょう。ただし、テーマによって結論の求め方や選考合格に必要な能力は違ってくるので注意が必要です。テーマに合った行動が振る舞いが出来るように準備しましょう。
①ディベート型
ある話題について、異なる立場に別れ話し合うテーマです。「大企業と中小企業はどちらがよいか?」「24時間営業は必要か不要か?」などのお題が出されるので、相手側とディベートをして自身の正しさを立証しなければなりません。
この課題の難しさは、自分の立場が勝つように論理を構築しなければならない点です。その立場を実際に支持しているかは関係ないので、本音は相手側のと同じ考えでも相手の味方をするのは厳禁です。また、ヒートアップしてしまうと意見の押し付け合いになってしまいディベートにならない場合があります。企業側はそのような状態からどのように持ち直すかを見ているので、ヒートアップしたまま終了するのはよくありません。
②課題解決型
「コンビニの売り上げを2倍にするには?」「人間の平均寿命を100歳にするには?」など課題の解決法を議論して編み出すテーマです。チームを組んで意見を出し合い、内容をまとめ、全員の前で発表するという手法がよく使われます。
このテーマでは、協調性はなによりも大事です。自分の良さをアピールしたいがために個人行動をとるのはマイナスとなります。協力し合って答えを出していく姿勢を意識しましょう。
③資料読み取り型
「資料を読んで会社の業績改善方法を考えなさい」「資料を読んで顧客のニーズを探してください」など、課題があらかじめ設定されており、それについての資料が付随している形のテーマが資料読み取り型です。この課題も、チームで行われる場合が多いテーマとなります。全員で資料を読んで、分析し、解決法を考えて発表するのが主な流れです。
資料読み取り型では、分析力が最も求められます。せっかくいい方法を考えついても、資料を読み間違えていた場合は効果的なものにはなりえません。分析力に自信がない場合は、チームのメンバーに分析を任せるのも一つの手です。
④抽象テーマ型
「無人島に一つだけ持っていくものといえば」「喜ばれるプレゼントといえば」など幅広い解釈の出来る抽象的なテーマが、抽象テーマ型です。自由に意見を出し合い、最も妥当と思えるものを議論しあいます。
このテーマは、あらかじめ答えが定められているわけではありません。最も高評価を得られる答えを想像し、論理的にそれを説明することが求められます。抽象的な分、しっかりとした論理を構築できるかがカギです。
以下の記事でもテーマ別の特徴と対策方法をご紹介しています。こちらも合わせて参考にしてみてください。
テーマ別グループディスカッション攻略法
それでは、各テーマ別の攻略方法を見ていきましょう。一番のポイントは焦らないことです。自分をアピールしたい余り早まった行動をとってしまうと、悪目立ちしてしまい企業側の評価が低くなります。時間は限られているとはいえ、自分をアピールするチャンスが最後まであるのがグループディスカッション(GD)の良い点です。焦らず、自分をアピールできるチャンスをじっと伺いましょう。
①ディベート型は柔軟さが求められる
ディベート型のテーマを乗り切るには、どんな時にも冷静に対応する柔軟さが必要です。
ディベートは意見がぶつかり合って硬直しやすいという性質を持っており、企業側はいかに硬直せず議論を円滑に進められるかを評価しています。意地を張って持論を主張し続けるのではなく、相手の主張の妥当性を認めつつも議論を展開する懐の広さを見せましょう。
議論を有利に進めたいなら、勝利条件の設定を主導するのがおすすめです。議論を始める前に「どこを争点とするのか」「何を証明すれば勝利したとみなされるのか」を話し合いつつ、自分の立場が有利になるように設定するのです。機先を制する形となり、議論全体を有利にすることができるのでぜひ行いましょう。
②課題解決型は現実的な意見を出そう
課題解決型は、いかに現実的な意見を出すのがカギとなります。課題解決型では、課題に対して現実に即した対応ができるかを企業側は確認しています。一見地味でも、堅実で確実な課題を発表できれば高評価を得られます。
意見が思い浮かばなかったら、企業側が求めている答えを想像して考えてみましょう。ある程度求められる回答が決まっているので、それを推察できれば効果的な回答を導き出せます。
③資料読み取り型は数字の読解力が求められる
資料読み取り型は、資料を正しく読み取れなければ答えを導き出せないという難しさがあります。特に数字を読み取ることが求められるので、資料に記載された数字は何度も目を通しましょう。
数字を読むのが苦手な場合は、他の人間に分析をゆだねるという手もあります。その代わりチームのリーダーとなって指示を与える、積極的に解決策を提案するなど自分にしかできない役割を果たすことに専念しましょう。
④抽象テーマ型は過程が大事
抽象テーマ型は、結論そのものよりそれを導き出す過程を企業は見ています。決まった答えはないので自由に回答できますが、強固な論理性がないと万人を納得させることができません。回答を発表する際は、なぜそのような結論に至ったのかをはっきりと表明しましょう。
過程をわかりやすく表明するために、図にして表現するという手法もあります。ほかの学生が発表するだけで精一杯になっている中、過程を図に書いてわかりやすく説明できれば評価はうなぎのぼりです。
まとめ
グループディスカッション(GD)は大企業を中心に行われているため、第一志望を大企業にした場合遭遇しやすい課題です。集団の中での動きが試される唯一の課題なので、効果的にアピールできれば後々の面接でも有利に立ち回れるでしょう。相手を尊重しつつ、有意義な議論ができるようにしましょう!
◼︎グループディスカッション (GD)の情報をもっと知りたい方にオススメの、就活Hack厳選ノウハウ記事はこちら









コメント